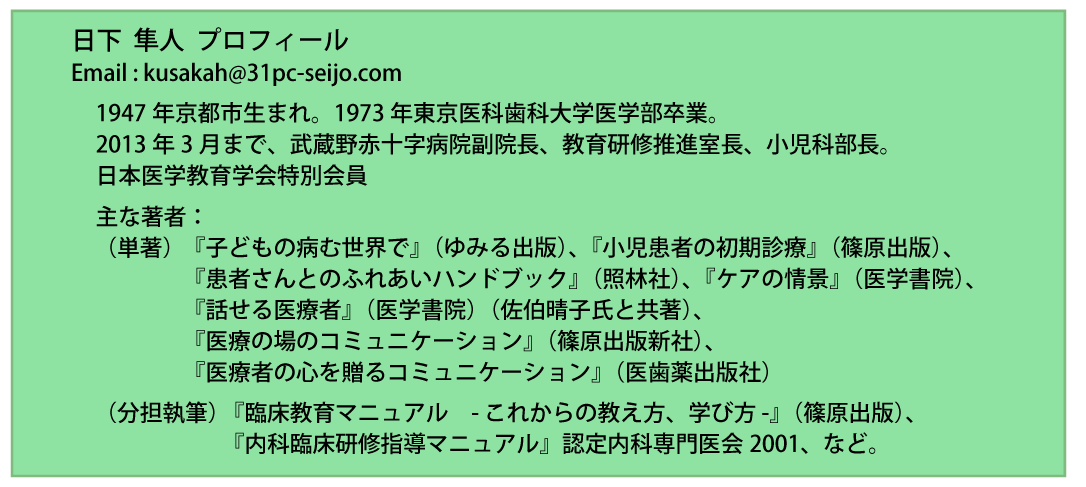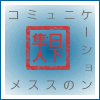 「良い医者」の存在が生権力を強化します。患者が「良い医者」と感じて医者を信頼する時、その信頼は医者個人に対してだけでなく、必然的に医学・医療に対しても抱かれます。こうして医療への信頼を深めることで、患者は自らの手で自分の首を絞めていきます。その医者がどのような思いを抱いていてもどのような実践をしていても(生権力に対して抵抗し続けていても)、患者から信頼されることで医者は生権力の「有能な」実践者の位置を占めます。「良い医者」を作ろうとする医学教育は、生権力を強化する「戦士」を作っていることから逃れられません。
「良い医者」の存在が生権力を強化します。患者が「良い医者」と感じて医者を信頼する時、その信頼は医者個人に対してだけでなく、必然的に医学・医療に対しても抱かれます。こうして医療への信頼を深めることで、患者は自らの手で自分の首を絞めていきます。その医者がどのような思いを抱いていてもどのような実践をしていても(生権力に対して抵抗し続けていても)、患者から信頼されることで医者は生権力の「有能な」実践者の位置を占めます。「良い医者」を作ろうとする医学教育は、生権力を強化する「戦士」を作っていることから逃れられません。
臨床医から研究者になった人が必ず言う「臨床もだいじだが、研究することでさらに多くの人を助けたい」という意味づけ(自己正当化)は、生権力をアプリオリに認める時にしか成り立ちません。社会的・政治的・経済的枠組みの中で研究課題が求められ(研究が「許され」)、自然科学的知からのアプローチが社会や政治に抵触せず、さらにその研究が社会のありようを強化するときにのみ、その研究の存在することが認められ、運が良ければ賞揚されます(ルイセンコの時代を嗤ってばかりはいられないのです)。
「医療不信」をなくすための努力や「医療安全」のための活動も、それが現在の医療の「安全」「安心」を保証しようとするものですから、同じ働きをします。
薬剤の適切な使用、障碍者医療、終末期医療、LBGTと医療、というように医療の在り方に異を唱える動きは次々出てきます。でもそれらさえ、医療の「欠落」を補うものとして速やかに「解毒」され、生権力の枠組みの一部として取り込まれていきます。生権力は、異議が生まれてくることはすでに折り込み済みで、そうした「異議」を不断に解毒吸収することでさらに強固なものになっていきます。そこにあるのは排除よりも限りない包摂であり、異議申し立て・抵抗の不可能性を私たちは思い知らされます。異議申し立てが速やかに生権力に吸収され、解毒化されたうえで何らかの変化を生み出すのですから、これまでなら非保守政党から選挙に立候補すると考えられていた障碍者や障碍児を育てている人、介護施設を運営している人が、保守の政権政党から立候補するのはおかしなことではないのです。
長々と書いてきたことは、今日ではむしろ「常識」として多くの人が知って(感じて)いるのではないでしょうか。そのような状況に対して積極的に対応できるのが優秀な医者だと考えている人も少なくありません。その次元で、研修医と指導医の利害・目標が一致していることのほうがずっと多いようです。
良い医者の存在が生権力を強固なものにするのですから、患者が「良い医者」を求めれば求めるほど、「良い医者」の育成に協力すればするほど、ますます自分を生命管理社会の囚人に追い込んでしまうという自家撞着。医学教育で「良医の育成」を目標にすればするほど、監獄であることを患者に感じさせない有能な看守を育成することになるという悲喜劇がそこにあります。
けれども、「いのちの瀬戸際」(これは文字通り「瀕死」という意味ではなく「いのちの危機を感じる」という意味で、病気の重症度とは関係ありません)の状況に直面したときには、人は生権力に支配される「生」に納まりきらない思いを抱かずにはいられません。「いのち」はどのように管理しても管理しつくされるものではありません。そのとき人は、生権力が指示する、ひたすら「健康」に向かって邁進する人生から「降ります」(それまでは、健康への回帰=「降りないこと」を目指し、さまざまな指示に従ってきました)。「健康がどうとか、そんなことはもう言っていられない。自分はこう生きたいんだ」と「居直る」しかなくなります。降りたときにあらためて、その人の基底的な、これ以上は絶対に譲りたくない自分の人生への思いが息を吹き返します(フーコーの言う残滓=システムから逃れる者・分類しきれない者・規範に従うことを拒む者、になります)。それは、ファミレスでの食事の選択のような、与えられた枠組みでの選択とは位相を異にする、自分の人生の選びなおしです。
H.マルクーゼは30年以上も前に「現代社会を転形して自由社会をもたらそうとするラディカルな変革は・・・人間存在の次元−そこで人間の根源的絶対的欲求と満足があらわれる『生物学的』次元−にまで達せねばならない」と言っています。(「解放論の試み」1974筑摩書房)
その「居直り」は、それを肯定する医者がそばにいることでずっと容易になります。ですから、「居直った」患者は、その思いを医者に投げかけます。でも、その思いは、生権力の網の目をかすめるために、雑談の中でそっと小出しにしか表明されないかもしれません。「他愛ない」話をしてもよさそうな雰囲気の医療者にしか話しません。話せる雰囲気がなければ、はじめから言いません。小出しにしていることを、患者自身意識していないかもしれません。小出しにした思い=言葉がノイズのようにあしらわれたら、その後はもう口に出しません。患者から見れば、些細な言葉に立ち止まってくれるだけで、その医者はきっと「良い医者」です。その患者の言葉や動作に何もひっかからなかった医者でも、患者の周囲の誰かが患者の言葉や動作の何かにひっかかっているという事実に立ち止まることができれば、それでよいのです(「なんだ、そんなこと、たいしたことないじゃないか」「気にしなくていいよ」と言って無視してしまわないということです)。気にかかった患者の些細な言葉や動作の意味を、自らに向かって気にかけ続けることがケアを生み出す源泉ではないでしょうか。
ナラティブアプローチや構造化面接にも意味はあると思いますが、「聞き出そう」「整理しよう」とする姿勢からは聴き取れないことがあるはずです。そうした言葉は、グラウンデッド・セオリーでは拾えなさそうですし、最近流行りのコミュニケーションについてのエビデンスにも「引っかからなさそう」です。些細な言葉は、医療者の手元の質問項目から漏れ落ちてしまうようなものなのです。それに、個人の語りがエクリチュールとして可視化されることにもまた、生権力に取り上げられてしまう危険があるのです。
研究に没頭していても(研究が自分の人生の最重要課題であっても)、営利追求ばかり考えていても、ある患者の言葉や動作が医者としての初心を刺激し、その医者の耳から離れなくなることがあります。「取るに足りない」言葉に耳を傾け、思いを受け止めようと立ち止まった医者は、患者と対峙することになります。「生権力」の網に医者も絡めとられていますから、目の前の患者の思いを聴いてしまったとき、その思いを受け止めるかどうかの葛藤が生まれます。逃げられるものなら逃げようとします。それでも逃げ切れないとき、患者との対峙は矛先を変えて生権力との対峙になります。
その葛藤を持つこと自体が、すでに生権力の枠をはみ出しています。生権力の支配する医療の枠組みを多少なりともずらさなければ、患者の願いに添っていくことはできません。思いを受け止めるために足を踏み出すことは、生権力に楔を打つことになります。医療の枠組みをずらすことは、システムに組み込まれていることを多少なりとも拒むことであり、そのことは医者自身が組み込まれている「健康」をシロアリのように内側から崩していくことでもあります。
システムから逃れることは、医学を否定することではありません。「医学の全否定」「“非科学的”医学」に基盤を置くこと、つまり「〇〇の治療を受けてはならない」「(病院で勧める医療より)こちらの主張する『医学』のほうが正しい」「こちらの言う通りにすれば良いことがある」と言うようなことは、生権力の占めている位置を奪い自らがその位置を占めようとする企てでしかありません。それは生権力と対峙するのではなく、権力の位置を同じ平面で奪い合うことにすぎません。
どのような「良い医者」であっても、患者を生権力に閉じ込める看守にならざるを得ないことから目をそらさないこと。その上で、患者という一人の人間と対峙し、その人の望む生き方を支えるために医療の土俵の外に足を一歩でも二歩でも踏み出してみること。それは、生権力を支えている医学的知識を基盤として、生権力のシステム(医学の知・医療制度の枠組み)にある程度依拠しながら、それでも生権力に完全にとりこまれないという「せめぎ合い」を医療現場で引き受けるということです1)。「健康、健康ってうるさいよ」という思いと「命あっての物種、健康が一番」という思いの間を揺れ動く患者の思いの両方につきあうということだともいえるかもしれません。(人を管理しつくしてしまっている)医療をきちんと実践することと、生権力に取り込まれることを拒んで患者と共に歩む医療を実践するという「せめぎあい」。この両極端のように見える医療を極めていくことは、ウロボロスのように接合しています。
生権力の作り出した構造に無自覚でいる医療者は「健康を失ってはじめて、そのありがたさがわかった」という患者の言葉に慰撫されますが、無自覚でいる限りそのせめぎあう日々を「楽しむ」ことはできません。そのようなとき、医者は患者を自らの意識から遠ざけることによって「楽しさ」を得ようとするのです。「楽しむ」ことを可能にしてくれるものは、患者とのおつきあいであり、患者の「笑顔」しかありえません。この笑顔は、医者が土俵の外に足を踏み出すことからしか始まらないのですから、関係は循環しているのです。でも、みずからの専門性を通して「いのちの瀬戸際」にいる人の笑顔を目指す人は、実は巧まずしてこの過程を生きています。「患者の笑顔を見たい」という思いは、ウロボロス状況を生き抜く力の源になりうると思います。
その人にとって自分の「いのち」が、最後の且つ最強の拠点ですが、その拠点すらも攻められているのが今日の状況です。人生最期の時という最後の砦さえ、「無益な治療」という言葉で陥落させられそうになっています。アドバンス・ケア・プラニングとして最期の時について患者と医療者との話し合いが勧められていますが、それは最期の時間まで生権力に支配されつくすということでもあります。QOLも医療者の操作対象として考えられる限り生権力の貫徹です。それでも、「患者の思い」には、生権力を揺るがすエネルギーが蓄えられています。
医者の教育で伝えるべきことは、臨床の場で何か課題が出てきたときにはいつも、患者のそばに行き、話を聞き、その思いから途を探す姿勢であり、教えるべきことは日々の診療の中に課題を見つける「視力」なのだと思います。その力は、フーコーを読み込むよりも(少しは知っておくほうが良いと思いますが)、患者の「(作り笑いではない)笑顔」を求め続けることで身につくはずです。医学教育は、この可能性に賭けてみるしかないと思います。採用面接での「病気の人の笑顔が見たい」という医学生の言葉は、貴重な言質なのです(個々の医学生に言質を取るということではありません)。(2016.05)
1) 「対峙」しようとする医者は、みっともなく右往左往したり、言うことが時と場合で違ってしまったり、相反する思いに引き裂かれたりと、「カッコ悪く」生きざるをえません。そのことを他人から指摘されるとされないとにかかわらず、医者は内心忸怩たるものを抱え込まざるをえないのです。